夫が亡くなったのは、結婚15年目で、未成年の子どもが二人いました。今は二人とも18歳以上です。夫が亡くなった時、あまりにも突然だったこともあり、ショックとこれからの生活の心配が一気に押し寄せてきました。私は仕事はしていたものの、全体の収入の20%ほどで、あとは夫の収入で暮らしていたので、正直、亡くなった悲しさよりも今後の心配の方が大きかったです。

まず心配したのは医療保険でした。医療保険は夫の仕事を通して加入していたので、夫が死亡したと同時に、保険の契約も打ち切られてしまいます。たしか、死亡した次の一か月間はまだ医療保険の契約が続けられていたと思います。亡くなって、2週間後くらいに保険会社から次の月には保険が切れるというような手紙を受け取った記憶があります。私はパートだったので、私の職場の健康保険には加入できませんでした。後程、夫の職場の労働組合から、子どもが22才までの間は子どもと私も継続して夫の職場の保険に入れるということが分かったので良かったのですが、そのことがはっきりするまではかなり心配しました。

心配事は医療保険だけではありません。生命保険には入っていましたが、家のローンに対する保険には未加入でしたので、特に夫が死亡したからと言ってローンがなくなるというわけでもありませんでした。毎月1000ドル近い家のローン、200ドルの車のローン、電気代、水道代、ごみ処理の費用などなど、、、。生活するために毎月かかる費用があります。幸い、我が家はハリウッド映画に出てくるような豪華な生活はしていなかったものの、それでも毎月お金はかかります。

日本に子供たちと一緒に日本に帰ることも真剣に考えました。結局アメリカに残ったのは、まずは子供たちが日本には行きたくないと主張したからです。また、私の地元の教育委員会によると、学年を落としての転入はできないということも、帰らないで留まる選択をした理由になりました。アメリカ育ちの二人の子どもたちはもう中・高校生になっていたので、言葉や学習面でかなり大変な思いをすることになったと思うので、今になってみれば、むりやり帰らなくてよかったです。結局1年後に家を売って、全く新しい土地に引っ越したので、アメリカ国内とは言え、子どもたちにとっては結構いろいろな負担をかけたと思います。
亡くなった1・2か月は今後の不安で眠れない日が続きました。食べ物も喉を通らず、このままでは体調を崩すと思って、無理やり食べた記憶があります。のちに、ソーシャルセキュリティーから遺族年金と夫の職場の労働組合からも遺族給付金(ごめんなさい、日本では何と呼ばれているのかわかりません。)が子どもたちが18才と22才になるまで給付されることがわかり、何とか生活できることがわかり、現在に至っています。

ここまで読んでくださった方々がいらっしゃったら、読んでくださってありがとうございました。今回初めて夫が死亡したときの状況を言葉にしてみました。あまりまとまっていませんが、文章で表現してみて分かったことは、自分の状況は割と恵まれていたということと、8年近く経ってもこの不安の感情は全然癒えていないことです。自分は夫の生前中に、もっと自立しておけば、ここまで不安に駆られなかったのかなあと反省しています。結婚していてもそれぞれがバランス良く自活できるくらいのほうが、どちらか一方に何か起こってもダメージが少なく済むと思います。
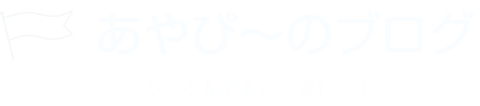



コメント